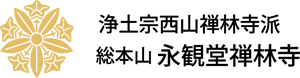南知多町 聖崎公園の河津桜 撮影: 超空正道
厭 穢 欣 淨
仏教が日本に伝来したのは西暦五三八年(日本書紀では五五二年)に百済よりもたらされたとする説が有力ですが、当初はもちろん、民衆にまでその教えが浸透していたわけではありません。法然上人によって、仏教の難しい教えや厳しい修行を自力では適わないような愚鈍の身であっても、阿弥陀仏の誓願である他力にすがり、ただ「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えれば、皆が皆平等に極楽浄土に往生できるという、革新的な専修念仏の教えが提唱されました。これはほかの仏教教団から強い反発や弾圧を受けることになりましたが、このことが契機となり、お題目「南無妙法蓮華経」を唱えればよいという日蓮宗、そして、只管打坐「只坐れ」という曹洞宗といったいわゆる鎌倉仏教が弘まるところとなり、一気に仏教が民衆の中まで溶け込んでいきました。
ところで、法然上人には多くの門弟がいましたが、浄土真宗の開祖である親鸞聖人もそのお一人です。我が西山禅林寺派の派祖証空上人の場合は、元服にあたり発心して十四歳で出家、法然上人の弟子となり、以来、臨終されるまでの二十一年間、その許で修学されたという、生粋の法然門下でした。法然上人が建久九年(1198)、時の権力者であった九条兼実の懇請を受けて『選択本願念仏集』を撰述するにあたり、引用文との照らし合わせという重要な勘文の役をつとめ、翌年には師法然上人に代わって、九条兼実邸でその『選択集』を講じられたと言われています。師の滅後に建保元年(1213)から京都西山善峰寺の往生院(三鈷寺)に住したことから、西山上人とも呼ばれ、その門流は西山三派、すなわち西山浄土宗・浄土宗西山禅林寺派・浄土宗西山深草派として今日まで綿々として伝えられてきています。その教えの一端を今回は味わってみようと思います。
西山上人の教義は哲学的で難解であると評されていますが、短編で比較的平易な『五段鈔』を取り上げてみます。その冒頭に、「夫れ速かに生死を離れんと欲はば浄土の一門に依る可し。之に付きて即ち五段有り、一つには穢土を厭ひ、二つには浄土を欣ひ、三つには三心を具し、四つには念仏を行じ、五つには念仏の益を明す」とあり、そこに『五段鈔』という名の由来を尋ねることか出来ます。紙面が限られていますので、その一段のみ、しかも格調高く古来より、法語「厭穢欣淨」として読まれている部分を原文にて紹介いたします。
四生無常の形、生有る者は死に帰す。哀れなる哉電光の命、草露の朝を待つが如し。悲しい哉風葉の身、槿花の朝にして夕にいたらざるに似たり。五蘊の仮舎に旅客の主、六趣を指して中有に生を求む。幽魂は無常にして濁り逝き代れば、質は山沢に残り骨を野外に曝す。
人中・天上の快楽は夢中にして幻の如し。八苦の悲しみ忽ちに来たり、五衰の患へ速やかに到る。地獄・畜生の果報は業に依りて感ず。八寒・八熱の苦しみを受け、残害・飢饉の患へ有り。或は鉄杖骨を摧き、刀林膚を割く。眼には獄卒阿榜の嗔質を見み、耳には罪人叫喚の声を聞きく。是の如く火・血・刀の苦しみ間無く億々万劫にも出で難し。
愚かなる哉。一旦の名利に依つて永く三途の沈淪を受んこと。拙い哉。此度生死の苦海を出でずんば未来何んが菩提の彼岸に到らん。
かるが故に三界六道を厭ひて常楽の門に入るべし。
【注】
①四生=生き物を生れ方により4種に分類したもの。胎生・卵生・湿生・化生(何もないところから忽然として出生するもので、天人や地獄の衆生)の4種。
②五蘊=色・受・想・行・識の5種。〈蘊〉は、集まりの意味。人間の肉体と精神を五つの集まりに分けて示したもの。
③六趣=六道とも。衆生が自ら作った業によって生死を繰り返す六つの世界。地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天の六つ。
④中有=中陰とも。前世の死の瞬間から次の世に生を受ける瞬間までの霊魂身とでもいうべき中間の時期(四十九日間)。
⑤五衰=無量の快楽を受ける天人さえ、六道に住する限り、死ぬ時は五つの衰弱の相が出て大苦を免れ得ないことをいう。
⑥阿榜=地獄の獄卒。牛頭で手は人のごとく、脚は牛に似て力が強い。
⑦嗔質=目を瞋らして口で嗔る様。
⑧三途=地獄・餓鬼・畜生の三悪道のこと。
⑨常楽の門=浄土宗のこと。
音読して先ず感ずるのは、実に気持ちよく唱えられることです。我々欲の深い人間でありますから、現世利益を願うことは致し方ないとしても、御祖師に思いを馳せて、ぜひ、折に触れこの「厭穢欣淨」を唱え、厭離穢土欣求浄土の生死問題に、しみじみ触れてみることも大切です。
(潮音寺 鬼頭研祥)