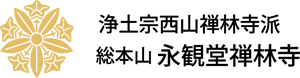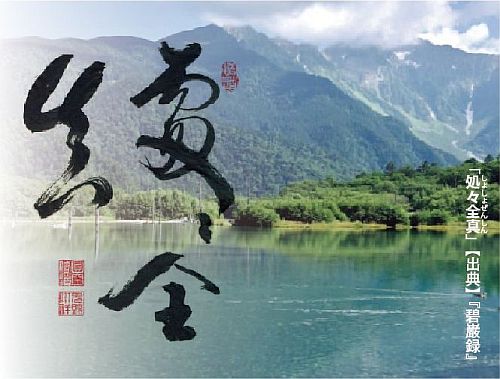
上高地の大正池 撮影: 超空正道
処 処 全 真
釈尊には多くの弟子たちがいましたが、特に十大弟子は、ぬきんでた才能を発揮された代表格の方々で、中でもその筆頭は、智慧第一といわれた舎利弗(舎利子、シャーリプトラ)でした。多くの経典にも、その名は度々登場します。あの短い『般若心経』でさえ二度、『阿弥陀経』にいたっては、さほど長い経典ではないにもかかわらず、釈尊は舎利弗の名を何度も呼びかけ、三十八回も出てまいります。
彼は、釈尊より年長であったといわれます。若いころから学問に優れ、当時もっとも有名な論客の一人で、徹底した懐疑論者サンジャヤの弟子でありましたが、親しかった目連と一緒に釈尊に帰依し、サンジャヤの弟子二百五十人を引き連れて集団改宗したということです。それには、こんなエピソードが伝わっております。
釈尊の最初の弟子は、出家後、苦行をともにした五人の比丘たちです。釈尊が、六年間に及んだ苦行は、身を苦しめるだけで菩提への道ではないと、村娘から乳粥を得たのを見て、彼らはいったんは離れていきました。しかし、釈尊が悟りを得た後、その説法を聞いて、最初の仏弟子となり、ここに初めて仏教教団が成立することとなりました。
その中の一人であった阿説示(馬勝、アッサジ)が、ある時、王舎城(ラージャグリハ)で托鉢していたところ、その凜とした姿や所作を見て感じ入った舎利弗は、阿説示の後を追い「あなたの師は誰で、どのような教えを説かれるか」と問いました。阿説示は「釈迦牟尼で、『諸法は因より生ず。また、それら諸法の滅をも』と説かれます」と答えました。
舎利弗は、その仏陀の教えの一端を聞いただけで預流果(悟りの最初の段階)に達し、親友であった目連と共に仏弟子となったといいます。そのため、舎利弗は阿説示に死ぬまで恩義を感じ、夜に寝る時も彼がいる方向には足を向けなかったとも伝えられています。つまり、舎利弗は、阿説示と出会う以前においても、二百五十人もの弟子を抱えるひとかどの権威であったのですが、その人をして、たちまちに釈尊の下に馳せ参じさせたものは、その教えである因縁の法(ダルマ)でした。
『般若心経』において、「舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨不增不減。……
(舎利子よ。色は空に異ならず、空は色に異ならず。色はすなわちこれ空、空はこれすなわち色なり。受想行識もまたまたかくのごとし。舎利子よ。この諸法は空相にして、生ぜず、滅せず、垢つかず、浄からず、増さず、減ぜず……)」のくだりは、まさに、舎利弗に対して、因縁の法、あるいは因縁生起(縁起)といっても同じことですが、それを空という概念で補講されている場面であるということです。
経典を読むに当たって大切なことは、この『般若心経』の場合、「舎利子(舎利弗)よ」と呼びかけていますが、それは他でもない、私に釈尊が呼びかけて下さっていると感じ取ることです。当然のことながら、はじめは理解できないことも多いかと思いますが、舎利弗に近づく努力を惜しんではなりません。
やがて、「此があれば彼があり、此がなければ彼がない。此が生ずれば彼が生じ、此が滅すれば彼が滅す。(小部経典『自説経』)の意味するところが理解できるようになると、世界観が大きく変わります。
すなわち、それまでは自分を中心とした利害関係や損得勘定から、事の善悪や真偽を判断していたことが、実は、自分という存在は、宇宙の大きな法則の中で、因縁の法に基づいて一つの現象としてあるのだということに気付かされます。そうすると、これまで「こんな理不尽なことはない!」と怒っていたことが、結局は、自分が知らず知らず蒔いた種が、原因であったということはよくあることです。
ただ、昨日の行いが即、今日の果報というものではありませんし、共業共果といって、他人と共有しうる結果をもたらす力が働く場合もあり、時空にずれが生じ、人知の及ばない面が当然あります。また、「縁起が悪い」「因縁を付ける」「親の因果が子に報う」「自業自得」といったことばは、どうも悪い意味合いで使われることが多く、暗いという印象も否めません。しかし、自然科学における万有引力の法則が、動かしがたい真理であると同様、因縁の法は仏教における核心であり、宇宙の真理であることに間違いはありません。
すなわち、いかなる場所においても、いかなる場面にあっても、すべてが仏法発露の場であり、たといそれが不合理、あるいは理不尽だと思えたとしても、すべてが、因縁生起の道理にかなった真実を具現しているということです。『碧巌録』にある「処処全真(至るところ、すべてが真実)」は、そこのところをずばり端的に表現しています。因を正しく見つめる眼と、縁に感謝する心を養っていきたいものです。
(潮音寺 鬼頭研祥)